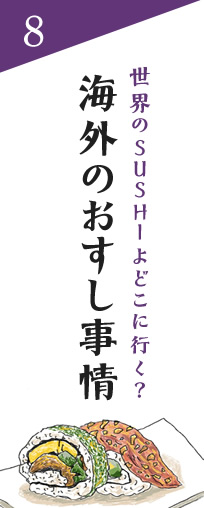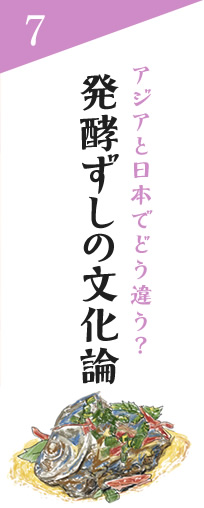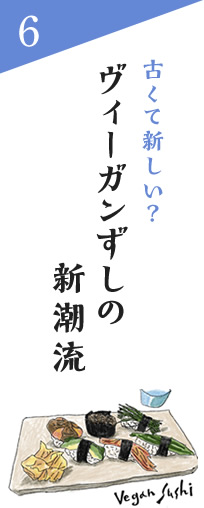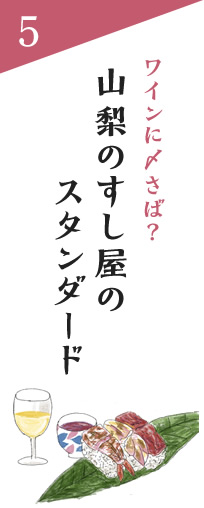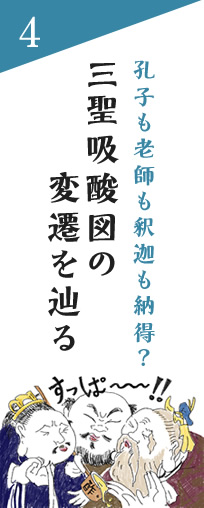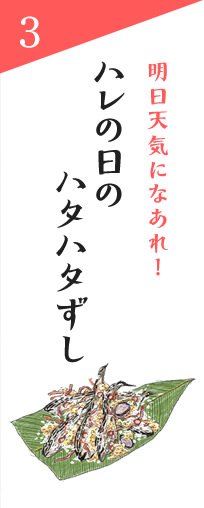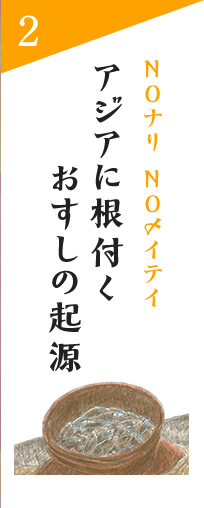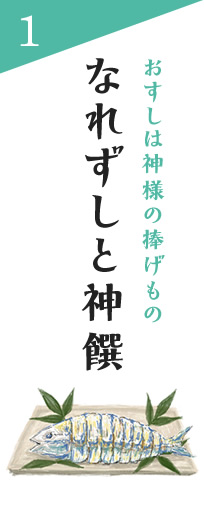第3回 ハレの日のハタハタずし
明日天気になあれ!
はじめまして。小倉ヒラクです。僕は「発酵デザイナー」という肩書で、日本各地の発酵文化を訪ねる仕事をしています。 この連載では、発酵の視点からおすしの文化を紐解いていきます。
神の魚、ハタハタ

白神山地のある、秋田県八森の海岸線。ふだんは演歌の世界のような荒々しくて人の気配がしない北の日本海の漁港です。
ところが冬のほんの数週間、年によっては数日だけこの八森の漁港が活気づくタイミングがあります。それは、岸にハタハタがやってくる瞬間。漢字では鰰(かみのさかな)と書く、秋田県民のスピリットを象徴する魚がハタハタ。
全長15cmほどの、ほどよく脂の乗った淡白な味わいの魚が、冬のある時期、突如として大群で海に押し寄せてきます。その様が神の奇跡のように映ったのでしょう。
到底一度に食べきることができない大量の旬の魚を腐らせないために、保存技術=発酵の出番となるわけです。
八森のハタハタフィーバー
シーズンに八森を訪ねると、堤防には釣り竿を持った地元民が一心不乱に釣りに励んでいます。クーラーボックスを覗くとハタハタがぎっしり!八森名物「ハタハタフィーバー」の始まりです。
このあいだだけ、普段は閉まっている港の近くの加工場がオープンし、地元のお母さんやお父さんたちが水揚げされたばかりのハタハタを大急ぎで加工するのですね。
保存用の加工方法は大きく2つ。まずは魚醤(しょっつる)です。ハタハタをアタマから内蔵までまるごと大量の塩の海に沈め、塩分の浸透圧と微生物の発酵作用でドロドロに溶かし、上澄みの旨味のたまった液体を濾したソースがしょっつる。
ベトナムのニョクマム、タイのナンプラーと同じカテゴリーの調味料ですが、東南アジアのそれと比べると、さっぱりなめらかな質感。寒い土地柄を利用して一年以上かけてゆっくり熟成させるのでこの品の良さが生まれるのでしょう。
もう一つの定番の保存食は、ハタハタずし。お酢で〆る現代的なおすしではなく、酵素作用を使う発酵ずしの一種です。ただ滋賀名物のフナのなれずしなどとは違い、お米とは別に、麹やお酒、野菜なども使って仕込む手が込んだ郷土ずしなんですね。
発酵ずし界の貴族
それでは作りかたを説明しましょう(製法は八森で訪ねたご家庭のもの。家によってレシピのディティールは変わります)。
ハタハタを塩漬けにして一日おきます。翌日塩を洗ってから今度は酢漬けに。甘じょっぱい味覚が好まれる秋田では、甘みを加えた酢を使うことも。一日酢漬けにしてから魚の身を取り出し、いよいよ本漬けです。
ハタハタに麹、飯米、刻んだニンジンや生姜などと混ぜて樽に漬け込み、二週間ほど発酵させたら、樽から取り出して麹や米ごと食べます。
もうレシピを聞くだけで絶対に美味しいに決まっている!とニヤニヤが止まりません。樽から取り出したてのハタハタのすしを食べてみてビックリ!生臭さや糠漬けっぽい風味がなく、ほんのり優しく甘く、旨く、品の良い酸味が得も言われぬハーモニーを醸し出しています。
そもそも淡白なハタハタを、酢や麹でソフトに漬け込んでいく…。ハタハタずしは「発酵ずし界の貴族」に認定したい!
このハタハタの飯ずし(いずし)は、沿岸部の魚介の文化と、内陸の田園地帯の麹文化が見事に融合した秋田の発酵マスターピース。爽やかでジューシーのある秋田の地酒と合わせてみたいものです。
ハレの食の原点
ハタハタずしを食べると、おすしの「ハレの日の食」としての原点が見えてきます。
高級な食材を外から買うのが難しい地域でも、身近な旬の素材に手間と時間をかけて、心が浮き立つような華やかな料理に仕上げる…。
甘くて、ほんのり酸っぱくて、淡白な脂身が口の中でホロホロと溶けていく…。普段は繊維質の野菜が主体になる伝統的なケの食卓と対になる八森の人々のお気に入りの味覚が詰まったおすしなのですね。
ハタハタ漁のシーズンに僕が訪ねた加工場は、「ひより会」という地元の漁師のお母さんの集まり。お母さん手作りのハタハタずしを食べながらこんな話を聞きました。
「ひよりというのは、明日船が出せるか天気の様子を見ること。明日は晴れるよ、漁ができるよ!という嬉しい気持ちを願いに、この名前にしたんです」
そんな浮き立つ気持ち、明るい明日を願う気持ちが郷土のおすしには込められているんですね。