
はじめまして。小倉ヒラクです。僕は「発酵デザイナー」という肩書で、日本各地の発酵文化を訪ねる仕事をしています。
この連載では、おすしエキスパートのシェフたちと、21世紀のおすし文化のスタンダードを考えていきます。
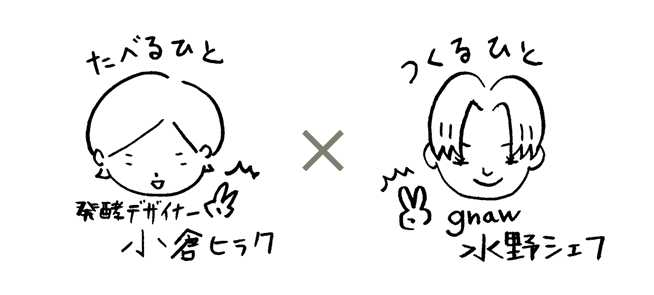
今回から趣向を変えまして、気鋭のシェフたちと一緒に未来のおすしのスタンダードを実作のかたちでリデザインしていきます。
今回ご一緒するのは、ミツカン本社と同じエリア、愛知県半田の亀崎という海沿いのエリアにあるgnawの水野シェフ。
彼は敷島酒造という老舗酒蔵のなかにキッチンを構える、発酵とおすしのエキスパート。海外のファインダイニングとのつながりも深く、世界最先端のガストロミーに精通している新鋭です。
さて。
今回水野さんがリデザインに挑戦したのは、
『なれずし』。
塩漬けした魚の身を開いて米を詰めて乳酸発酵させた、発酵ずし、いや全てのおすしの原点とも言えるレシピです。

なれずしで最も有名なのは、滋賀のフナずし。魚の頭と内臓を取り、塩漬けに。その後、開いた身に飯米を詰め、同じく飯米を敷き詰めた樽に漬け込みます。漬け込んでいるあいだはしっかり重しをして空気を抜き、さらに表面に上がってくる魚の水分を丁寧に洗いながら数ヶ月〜2年ほど長期発酵させてできあがり。魚のチーズのような深い酸味とうま味が特徴です。
さて、このなれずしを水野シェフはどのように現代の食卓に合わせてリデザインしたのか?

見た目はおすしというより、スープ…?スプーンですくって食べていると、発酵の酸味の効いたおじやのような味。なれずし味のおじやの中に、また異なるなれずし。さらに魚卵の珍味のような味。これは今まで全く食べたことのない味!いったいどのようなデザインなのか?
構成を分解してみましょう

メインの具材になっているなれずしはサバ。塩と合わせて下漬けしたサバともちごめを合わせて、一ヶ月ほど発酵させて仕上げています。フナずしよりも発酵期間が短い「はや漬け」と呼ばれるスタイルです。
おじやは、昨年漬け込んだイワシのなれずしの飯米の部分(飯と書いて”いい”と読みます)をアレンジしたもの。こちらは一年発酵させた「ふか漬け」です。
さらに付け合わせはボラの魚卵でつくったカラスミの一種のよう。血と水分を抜いたカラスミをピータンのように灰を使って熟成させ、さらに蜜蝋でコーティングして仕上げた水野シェフの独創的な製法です。
もはや書いてる僕すら理解が追いつかない、複雑な技術と味わいのオンパレード!
おじやって普通は〆でサラッと食べるもの。味わって食べるにはちょっと味わいが単調です。
ところがこのなれずし×カラスミおじやはひとくちずつじっくり味わえる複雑なレイヤーを持っています。
僕なりにこのレイヤーを表現してみると「酸味のデプス(深度)を分けてレイヤー状に構成している」ということになるでしょうか。サバのなれずしは魚自体の食感を活かしたフレッシュな酸味。イワシのなれずしの飯(いい)のおじやは熟れた酸味、そしてカラスミは様々な要素を含んだ華やかで複雑な酸味。この三つの酸味を立体的に構成することで、食べる人の酸味に対する解像度が強制的に上がってしまう。
これは食の好奇心を満たしまくる、すばらしいエンターテイメント。さて、このようなユニークなレシピはどんなコンセプトで生まれたのでしょうか? 水野シェフに聞いてみました。
“100年先も作れるレシピをテーマにしています。伝統的ななれずしは熟成期間が長く、お店で日常的に出すのは難しいので短期発酵のはやなれにしています”
“異なる発酵技術と発酵期間、魚種を使い分けて酸味にレイヤーをつくっています。そのことによって単調にならず一皿のなかで色んな味の体験ができます”
“サバもイワシもボラも三河湾で獲れる魚介です。とりわけボラはたくさん獲れる魚。たくさん獲れる魚を保存するのが発酵の基本なので、このような料理にしました。土地でとれたものから豊かな味のバリエーションをつくる。それが美味しいから100年続く。そういうレシピを目指しています”
三河湾でそんなにも多様な魚が獲れるとは思ってもみませんでした。伝統にこだわりすぎると現代的なレストランで気軽に出せない、という気づきも水野さんの飲食業界全体を考える課題設定力の強さを感じました。素晴らしい!
それでは次回は新たなシェフを招聘し、21世紀のおすしスタンダードのデザインに挑戦します。どうぞお楽しみに!

















