
はじめまして。小倉ヒラクです。僕は「発酵デザイナー」という肩書で、日本各地の発酵文化を訪ねる仕事をしています。
この連載では、おすしエキスパートのシェフたちと、21世紀のおすし文化のスタンダードを考えていきます。
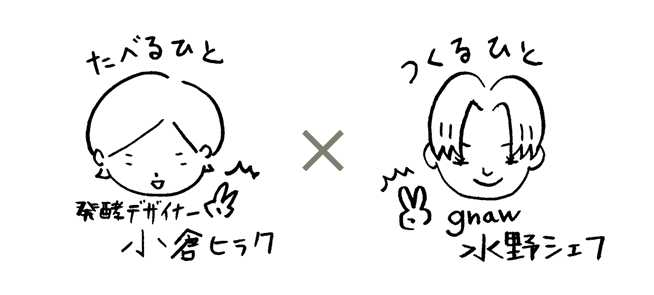
今回から趣向を変えまして、気鋭のシェフたちと一緒に未来のおすしのスタンダードを実作のかたちでリデザインしていきます。
今回ご一緒するのは、ミツカン本社と同じエリア、愛知県半田の亀崎という海沿いのエリアにあるgnawの水野シェフ。
彼は敷島酒造という老舗酒蔵のなかにキッチンを構える、発酵とおすしのエキスパート。海外のファインダイニングとのつながりも深く、世界最先端のガストロミーに精通している新鋭です。
さて。
今回水野さんがリデザインに挑戦したのは、
地元亀崎の郷土ずし、『箱ずし』。
木箱のなかに酢飯を詰め、そのうえに魚介や野菜、卵焼きなどを敷き詰め、米と具材を上からギュッと型押ししたおすしです。

半田の地区によって、カラフルな具材を斜めのストライプ状に敷き詰めた絵画のようなスタイルもありますが、gnawのある亀崎では酢飯の上いちめんに煮アサリを敷き詰めた素朴なもの。
さて、この箱ずしを水野シェフはどのように現代の食卓に合わせてリデザインしたのか?


おお!なんか海外の高級レストランのコースで出てきそうなハイセンスな見た目。小さな木枠に詰まったおすしの上に、巻かれた牛肉と大根、そしてその下には敷き詰められた卵焼きが見えます。
型をスポッと抜いてみると、いろんな具材と酢飯が段重ねになっているぞ?
構成を分解してみましょう
伝統的な箱ずしでは、酢飯の上に具材が乗った一層構造。しかし水野シェフは酢飯+具材のレイヤーを二層にしました。
“現代人は昔の人ほどお米をたくさん食べないため、米の層を薄くし、かつ食べる時の味のバリエーションを多くして食べ飽きないようにした”
とのこと。なるほど。確かにお米がみっちり詰まった箱ずしは、一切れ食べるだけでお腹いっぱいになってしまいます。二層構造にすればお米の量が減り、同時に具材のバリエーションが二倍になってエンタメ感が増します。
これは良い着想!
まだまだ仕掛けがたくさんあります。下の層は、赤酢(山吹)と塩のみのシンプルな酢飯。上の層は酢と塩に甘みも加えたより食べやすい酢飯になっています。米と具材の食べ合わせを、お米側でも調整しているのですね。この工夫により、下と上で酢飯を口に入れた時の印象が微妙に変わって興味が惹きつけられます。
一見した時に目に入るのが、艶めかしく輝く牛肉。肉の下には卵としいたけ、酢飯のリッチな一層目。さらにその二層目にアサリが出てきます。
牛肉とアサリを行ったり来たりしながら口のなかに溢れ出てくる、異なるうまみと酸味のハーモニー。なんという極上SUSHI体験…!
味的にももちろん素晴らしいのですが、この構成にも水野シェフの鋭い問題意識が込められています。
“現代では昔のように三河湾でアサリがたくさん捕れません。なので、この箱ずしではサイズが不均一で市場に出せない規格外のアサリを使っています。それでも伝統的な箱ずしのようにいちめん分厚く敷き詰められないので二層にしました”
“おすしはごちそうです。なので現代のごちそうである牛肉を使いました。伝統の型を守ってアサリだけでおすしをつくると、地域外、海外からアサリを運んでこなければいけません。それは郷土の料理と言えるでしょうか?”
“私は生産者の視点で料理をつくりたいと思っています。アサリを捕る人のことを考えると、形の揃ったアサリをたくさん用意するのは難しく、不揃いのものでも量はじゅうぶんじゃない。そこで地元の牛肉とも組み合わせて新しい郷土のごちそうをつくりました”
地元の食材を使うことに徹頭徹尾こだわる水野シェフ。味付けも山吹のような地元の調味料を使うだけでなく、アサリの味付けはアサリを塩で漬け込んでつくったアサリ魚醤を使っているそうです。
意識もテクニックも先進的すぎて言葉が出ない…!
それでは次回も水野シェフと21世紀のおすしスタンダードのリデザインに挑戦します。どうぞお楽しみに!

















