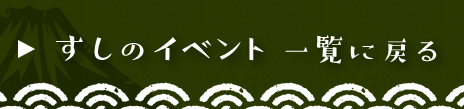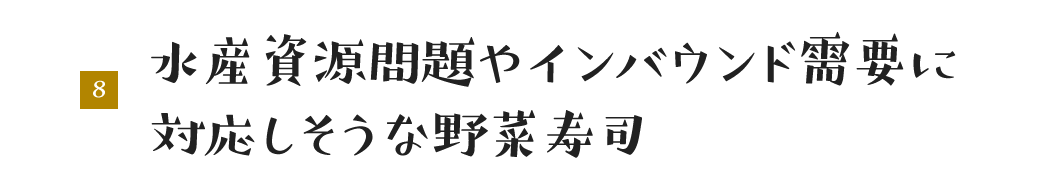
某調査では日本人が好きな料理をリサーチすると、断トツ一位が寿司。二位以下の唐揚や焼肉・餃子を大きく離しているそうです。一方、小学生を対象にすれば、①寿司②ラーメン③カレーライスの順となります。何はともあれ、大人であれ子供であれ、最も好きな料理は、寿司なのでしょう。ただ小学生調査の面白い所は、嫌いな料理が焼き魚、サラダ、刺身の順。これを見ると、別に魚が好みではなく、素材より調理法で好き嫌いが生じている事がわかります。殊、子供の場合は回転寿司の影響が大きく、回転寿司の普及によって一位に寿司がランクインされたのかもわかりません。



魚を使う料理の代表格として握り寿司が挙げられます。ところが、地球温暖化などの要因も加わり、天然魚が年々獲れなくなっているのです。おまけに海外諸国までが握り寿司の良さに着目し、水産資源を買い占める傾向にあって日本が他国に買い負けているとの話も伝わってきます。そうなれば、近い将来、魚介類を用いた寿司に危機が訪れるといっても過言ではありません。そんな危機を孕んでいながらもますます寿司人気は過熱気味。インバウンド客の目的が「本場で寿司を食べたい」というものが多く、訪日客の約7割が寿司を食すとまで伝えられているのです。
水産資源の枯渇による寿司ジャンルのダメージに一石を投じようというのが野菜寿司。昨今、本格的な寿司屋でも彩りのきれいな野菜寿司がちらほらお目見得し、魚介類の握り寿司にバリエーションを持たせているようですが、何も寿司に野菜を用いる行為は今に始まったわけではありません。巻き寿司には椎茸や干瓢、キュウリも使っていますし、ちらし寿司とて蓮根や人参、椎茸も入っています。ならば、昨今流行しつつある野菜寿司とはどんなものを指すのでしょうか。
寿司といえば、大半の人は握り寿司を思い浮かべるので、昨今注目を集める野菜寿司も当然、野菜をタネにしたもの。巷で見られる野菜の握り寿司は、単に野菜をタネにして握っているものが多く、それでは味の良さも面白みも欠けてしまいそう。そこで有名な寿司職人の川澄健さんに今後注目されそうな野菜寿司を作ってもらいました。ちなみに川澄さんは、自店「すし川澄」を長年営んだ後、寿司の技術を広めるために東京の寿司学校で講師を務め、寿司調理師の養成に携わって来た人物で、テレビ東京の「TVチャンピオン」全国寿司職人握り技選手権で三度の優勝を果たした実績もあります。

そんな川澄さんは、「野菜を用いる事で一般の握りより手間がかかります」と言い、ただ利点の一つとしては「傷みにくいのがいい」と指摘してくれました。今回、川澄さんがより美味しく食べさせる技を駆使して作ってくれたのが、写真の野菜寿司です。木桶に並べられた野菜寿司を紹介すると、最上段にキュウリの細巻き。金山寺味噌を入れて裏巻きにしたものを桂剥きして甘く煮た人参で巻いています。二段目は交互にカボチャのペーストを使った手毬寿司(上に黒豆の煮たものが載っている)と輪切りにしたズッキーニを焼いた手毬寿司を。三段目は左から茄子焼きロール(生姜醤油で)、人参の細切り甘辛煮、塩茹でしたアスパラガス、茄子の素揚げ(生姜醤油で)、パプリカの細切り甘酢漬(小松菜の帯)。四段目は左からカボチャの細切り素揚げ、アスパラガスの天ぷら、皮を剝いて茹でたパプリカの甘酢漬(小松菜の帯)、蒲焼きのタレを塗ったズッキーニの天ぷら。最下段には茄子の漬物(人参の帯)という握った野菜寿司を配しています。


これらが秀逸なのは、単に野菜を用いて握っているだけではなく、素材各々に仕事を施している点。いわば寿司職人の技が見え隠れしているのです。今でこそ握り寿司の大半は、新鮮な生の魚介類を使って握りますが、冷蔵技術がなかった江戸時代は、下処理したものが一般的でした。握り寿司は、江戸後期に江戸市中で誕生したのですが、当時はタネの種類も少なく、①酢に漬ける②醤油に潜らせる③火を通す④醤油・みりん・あく引きなどで煮る⑤その他(二杯酢に潜らせる・調味液に浸すなど)といった工夫をしてからタネに使用していたのです。今回の川澄さんの野菜寿司は、古くからあった手法を今流にして作ったもの。まさに“温故知新”の野菜寿司ともいえるでしょう。
近年増加する来日観光客の一部は、伝統的な寿司の作り方を知りたく、握り寿司体験施設まで足を運び、魚の捌き方を覚えて帰る人までいるそうです。ならば、握り寿司が生まれた頃から伝わる下処理の技法も参考になると思われます。特に欧米など海外からの訪日客は、ベジタリアンも多く、そんな嗜好が野菜寿司には表れているはず。しかも彼らの多くは生臭さを嫌い、握り寿司を敬遠する人までいます。別に魚の味が嫌ではなく、生の匂いを嫌うようです。ならば野菜寿司は、そんな条件をも満たしているといえるでしょう。水産資源の枯渇問題からインバウンド客対策まで幅広く使えそうな野菜寿司が今後注目されてもおかしくはありません。