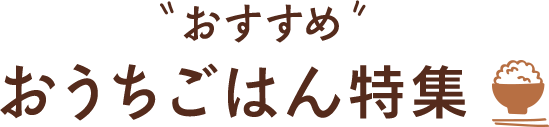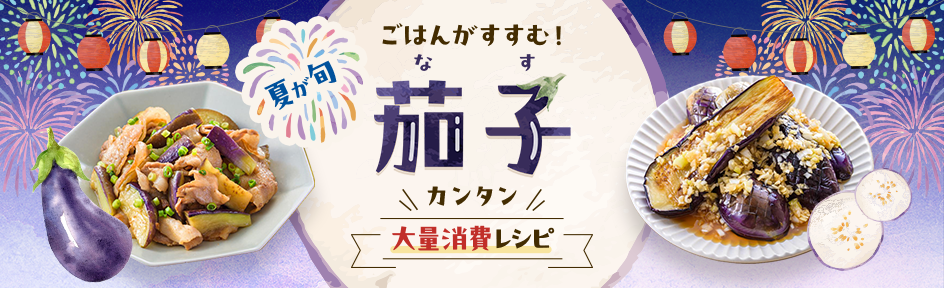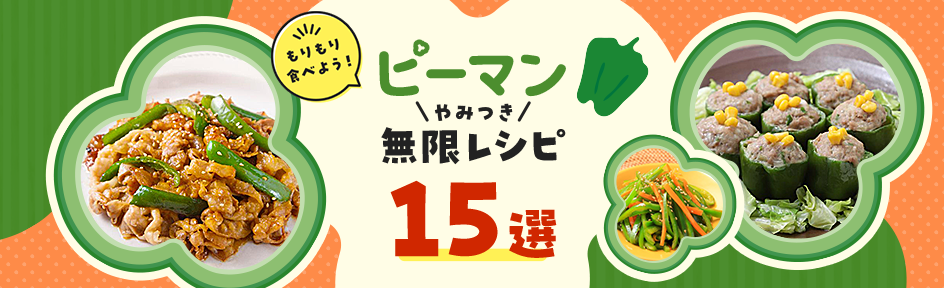料理の基本 ―覚えておきたい料理の基本―
料理を始める人がそろえるべき道具とその理由
そろえるべき道具
(1)材料をそろえ、煮炊きするための基本の調理器具

フライパン
できればサイズ別に、直径20cmと26cmのものを2つ持ちたいです。素材は色々凝るより、フッ素樹脂加工のもので十分。軽くて、中性洗剤で洗うだけですむので、管理が簡単です。また、2つともメーカーやブランドを一緒にした方が、ハンドルの持ち具合や底面の温まり具合を把握しやすいと思います。フライパンは同じものを使い続けるより、傷んだら買い替える調理器具、そう思えば気が楽です。
20cmサイズは、1~2人分の焼き魚、ハンバーグ、ソテーなどに向きます。さっと取り出せるサイズなので、すぐに何か焼くときに便利。最近のものは深さもあるので、これでかぼちゃの煮物や肉じゃが、煮魚も作れます。
26cmサイズは、1~2人分の炒め物、チャーハン、パスタや、鶏肉を2枚分焼いたりする時などに必要で便利な大きさです。添えの野菜と肉が一緒に焼けるサイズです。
包丁
まず、刃渡り15~20cmの万能包丁といわれるものを購入しましょう。素材はステンレスが管理しやすく、価格は5000円前後のものをお勧めします。あまり安くて軽いのは、切れ味がすぐに悪くなるからです。また、体に合った長さと重さも重要。切りながら刃を引く、刃を下ろす…と、包丁の重みによってリズムをとりながら切っていくからです。また、刃の幅も肝心。刃の幅が狭いと、切り下ろす作業が細かくなり、時間も長くなるので、却って疲れます。
まな板
お勧めのサイズは 25cm×35cm。大きいようですが、調理台から流しにはみ出した場合でも安定感が保てます。このくらいのスペースを確保することで、白菜・大根など大きな野菜を切ったり、まな板を左右半分ずつや上下左右四分割して部分的に使えるので、いちいち洗わずに済みます。厚さは1.5~2.0cmのものがよく、多少重いのですが、この重さにより安定します。また、このくらいの厚みは、包丁の当たりが柔らかいものが多いこともおすすめする理由です。
樹脂製はトントンと音がして、特に包丁が鋼でない場合は、包丁の衝撃を吸収しきれずに腕が疲れてしまうことが多いので、できるだけ包丁の当たりが柔らかなものを選びたいですね。木製(ひのき・イチョウ・桐・オリーブ)は包丁の当たりもよく、疲れにくいので、その点ではお勧めしたいのですが、高価で、乾きにくいことが難点。加えて、使い方によっては湾曲したり、脇に黒いカビが生えたり、毎日の調理で表面が削れてしまうなど、メンテナンスを必要としますので、慣れないうちは、漂白もできる樹脂製がよいと思います。
鍋
鍋も同じブランドやメーカーでそろえるようにすると、形や素材がある程度同じなので、調理していて、焦げるところや汚れるところ、水分の蒸発の具合、余熱の加減などの感覚がつかみやすくなり、火にかけた時の迷いが最小限に抑えられます。形はもちろん、調理器具の色が混在しないことも、意外と大切。キッチンがすっきり片付いて見えて気持ちよく、それだけでも料理のストレスが減ることにつながります。
2~3人分に使う鍋の大きさは、直径20cmの両手鍋と16cmの片手鍋からスタートしましょう。まずは2種類で使い勝手を試し、使う感覚を覚えていきます。
20cmは、煮込みや炒め煮などに、16cmは味噌汁、下ゆでなどに使いやすいサイズです。家庭の熱源では、広い径のものより、小さめでも深さがあって対流が良い方が使いやすさにつながります。
鍋は軽いほうがよいと思いがちですが、ある程度重さがあるほうが、安定感、密閉性、保温性の高さにつながり、軽いものよりも調理の感覚がつかみやすくなります。フライパンと違って、鍋は長く使うものと考え、予算が許せば多重層のステンレス製がよいと思います。ステンレス面がヘアライン加工してあれば、傷ついたり汚れても、あまり目立ちません。
(2)手に持って使う調理器具

菜箸
ひもがついている場合は、可動域が広がるよう、ひもを切って使います。また、長いものは意外と使いづらいので、短めのものをお勧めします。
耐熱性ゴムベラ
混ぜたり、炒めたり、フライパンをこそげたりと万能な調理器具です。ゴムが堅めの製菓用がおすすめです。
トング
焼いている具材を返したり、炒めもので上下を混ぜたり、サラダを和えたり、パスタを盛り付けたり、料理を取り分けたりと、とにかく何にでも使えるので、自分の腕の長さに合わせて使いやすい長さのものを選びましょう。
お玉
ソースや汁物を盛り付けるには欠かせません。片口のレードルより、丸いお玉のほうが、可動域が制限されず、使いやすいと思います。
ミニゴムベラ
意外と便利なのが、ゴムの部分が細いミニサイズ。粘性のある味噌やジャムなどを取り出したり、混ぜたり、素材や調味料を残さず無駄なく使うのに欠かせません。
(3)その他

ボウル
できればステンレスやアルミ製の軽いものを。食器で代用していた作業をボウルにすると手際も良くなります。サイズ違いが用途別に3種類(直径10cm前後・15cm前後・20cm前後)あると便利です。
10cm前後は、調味料を混ぜたり、少量の肉や魚の下味付けに。
15cm前後は、挽肉だねを混ぜたり、切った具材を用意しておいたり、いろいろに。
20cm前後は、水を入れて野菜を放ったり、パスタを和えたり、具材を丸ごと入れたり。サイズが違うと収納もコンパクト。使うときも、場所をとらずに重ねられます。
ざる
できれば、直径15cmと20cm前後の手つきの万能ざるが2つあると便利です。15cmは水切り、ゆで野菜などゆでもの揚げに、また、2合程度のお米を研いでも。麺類やサラダをよく食べるなら、水切り、湯切りに20cmのサイズが便利です。
大さじ、小さじ、計量カップ
1回に、大さじは15ml、小さじは5ml 計量カップは200ml、量れるように決まっています。量ることは面倒かもしれませんが、これらを使いながら調味料の分量を感覚で覚えるための目安だと思って習慣づけましょう。計量する他に、さじは調味料やソースを混ぜる際に使え、計量カップもこの中で混ぜるための小さいカップとして使えます。
タイマー
スマホでも代用できますが、キッチンでは油汚れの心配があるので、調理専用のものを用意します。経験のないうちは、煮込んだり、炒めたりする時間を、〇分煮るとこうなる、〇分炒めるとこうなる、と時間経過による見た目の変化や、食べた時の変化を確かめて、時間とその感覚を合わせて覚えるようにしましょう。
レシピのギモン…実際にはどうすればいいの?
料理が身近に感じられるようになるひとくちメモ
(1)「フライパンに適宜の油を熱し」は、実際どうすればいいの?

「フライパンを熱する」の火加減は、基本的に「中火」です。
「中火」は、炎がフライパンの底にあたるか当たらないかの火加減で、他に火加減の指定がある場合には、
「強火」は、炎がフライパンの底にあたって形が広がる程度、
「弱火」は、炎がフライパンに当たらない状態のイメージです。
最近は炎の量が制限されているガスレンジも多いので、こういった感覚で覚えます。
さて、「適宜の油」の量ですが、直径26cmで調理するなら、油は大さじ1、
20cmで調理するなら、大さじ1/2を目安にしてください。
最後に「熱する」は、素材に火を通すために、温まったフライパンと油で熱をいきわたらせる必要があるので、きちんと温めます。きちんと「熱する」目安は、中火で1~2分。フライパンの材質や厚み、その日の気温によって多少の差はありますが、素材を入れてジュっと音がするまでの時間と覚えてください。
(2)なぜ「塩を入れてゆでる」の? その後はどうしたらいいの?
塩を入れてゆでる理由は、目的によって複数あります。
① 野菜を茹でるときに塩を入れるのは、その目的別に大きく3つ。
A.下味をつける →ゆでながら素材に浸透圧が促され、素材に味がつく
B.繊維を柔らかくする →野菜の細胞と塩の成分が結びついて崩れ、柔らかくなる
C.色鮮やかにする →塩を加えることで青野菜の色素が安定しやすくなる
この時に有用な塩の量は、茹でる湯量の1.5~2%ですが、お湯をきちんと沸騰させておけば、塩を加えなくても、B、Cは解決できます。大事なのは、塩を加えるよりも高温であること。そのため、もし手間だなと思ったら、ゆで湯の温度を十分に上げておけば、塩を入れなくても大丈夫です。
また、ゆで時間の目安ですが、
ほうれん草・小松菜・菜の花などの葉野菜は、1分
ブロッコリー、アスパラ、さやいんげん、スナップエンドウなどは、2分
と覚えましょう。いずれもすぐに経ってしまう時間なので、むしろ、ゆで過ぎに注意しましょう。
② ゆでたら、必ず水に取らないといけないか
水に取った方がよい野菜、水に取らなくてもよい野菜があります。

・緑の濃い野菜に含まれるクロロフィルは、熱に弱いので、なるべく短時間に高温でゆでることが基本です。ほうれん草はアクの成分が多く、ゆでた後、ゆで湯の水分がついたままだと退色が早いため、水に取るようにします。菜の花もほうれん草ほどアクの成分は多くありませんが、ゆで湯に色素が溶けだす量が多いので、水に取る方が色良くなります。
・その他の野菜は、水にとらなくても大丈夫。水に取ることで早く温度が下がり、退色を防げますが、この時十分に水を切らないと水の味がしてしまいます。
ゆでた野菜はざるに取り、すぐに空気にあてておくことで、根菜など角切りにしてコロコロした野菜は、水気も十分に切れて色よく冷めていきます。ざるに上げた時の湯が、冷める際の水蒸気となって表面が乾くので、旨味が凝縮されて風味も保たれ、味つけの調味料も絡みやすくなります。葉野菜の場合は、冷めたら軽く水気をしぼって使います。いずれも水に取らないがほうが、甘味を感じやすいようです。
この際に余熱で火が通りやすいので、手早くざるあげすることが肝心。ゆで時間は短くしても良いくらいです。このように、水に取らずにおくことを「丘あげ」といいます。
(3)パスタをゆでる時に塩は必要?どのくらい入れればいいの?
パスタをゆでるときに塩を入れる理由もいくつかあります。
① 湯の温度を上sげる
② パスタのコシによる食感を上げる
③ 下味をつける

湯の温度を上げるには、相当量の塩を入れないと難しいことが分かっています。
また、塩を加えることで、パスタのでんぷんが締まり、コシが出てアルデンテに仕上がりやすく、塩を入れないと、締まらずに表面が開いた感じでざらっとしてしまいます。ですが、もたもたして、食べるタイミングが遅れると、結局アルデンテは逃してしまいます。
そのため、塩を入れるのは、「味付け」が主な理由と考えます。ひとくちに塩味といっても、パスタのメーカーや、生パスタか乾麺か、オイルパスタにするかトマトソースかクリームソースにするかで、塩味のつけ方の提唱は様々ですが、「ゆで湯量に対して1~1.5%」が基本です。湯1Lに塩10g(小さじ2)の見当です。
そうめんやうどんと違い、塩を加えずに製造するパスタは、そのままでは粉の味を感じにくいため、適度に塩味があることでうまみを感じます。
また、オイルベースのメニューの場合、オイルに塩が溶けにくいので、塩分の下味をつけることで、味なじみが良くなります。トマトソースやクリームソースも、後でソースを和える際に、この塩分が味なじみを良くしますが、特徴あるソースの味を生かして絡める場合は、下味の塩を入れないこともあります。パスタのコシより、もちもち感を生かしたいときのナポリタンも、塩を加えずにゆで、後からトマトケチャップなど、濃いめの調味料をなじませることもあります。